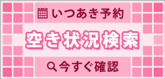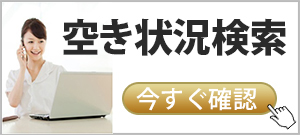2025.12.11
母親研究所では、毎年、年末機関にカウンセリングの無料相談を行っております。
期間は12月22日から27日まで。
時間帯
午前9時~
午前9時半~
午後20時~
午後20時半~
お申込み方法
1,氏名
2,メールアドレス
3,相談内容
4,相談希望日、時間帯
5、申し込みは,
メールアドレス:sakamoto@hahaoyaken.comまで。
個人の秘密は守ります。安心してご相談ください。
新生児のしつけは「お母さんの心の安定」から。0歳児との向き合い方と安心の育て方
2025.11.20
生まれたばかりの赤ちゃんは、1日のほとんどを眠って過ごします。
目を覚ますのは、お腹がすいたときや、おむつがぬれて気持ち悪いときなど、ほんのわずかな時間です。
初めて抱っこをするお母さんにとって、首のすわらない赤ちゃんはとても小さく、まるで壊れ物のように感じるでしょう。
しかし、赤ちゃんは生まれた瞬間から、外の世界を五感で感じ取る力を持っています。
抱かれたときのぬくもりや、授乳時のお母さんの声・表情・息づかいを通して、赤ちゃんは安心感を得ているのです。
お母さんの精神的安定が赤ちゃんの「安心感」をつくる
赤ちゃんは、お母さんの表情や声のトーンから感情を読み取ります。
お母さんが穏やかでリラックスしているとき、赤ちゃんも落ち着いて過ごせます。
反対に、疲れや不安、イライラが強いと、赤ちゃんも不安定になりやすくなります。
育児中は睡眠不足や心身の疲れが重なり、気持ちに余裕がなくなることもあります。
しかし、「泣かれても落ち着いて対処する」「完璧を目指さず、できる範囲でやる」ことが何より大切です。
お母さんの精神的な安定が、赤ちゃんの心を守る最初の「しつけ」なのです。
赤ちゃんは「親の感情」を敏感に感じ取る存在
首がすわる頃になると、赤ちゃんは笑ったり声をあげたりして、感情を表現しはじめます。
お母さんが優しく話しかけると、嬉しそうに反応するのはそのためです。
赤ちゃんは言葉の意味を理解していなくても、
「声の調子・表情・スキンシップ」
を通して安心を感じ取っています。
そのため、怒った顔や荒い声で接すると、赤ちゃんは不安を感じ、情緒の安定を妨げてしまいます。
お母さんの穏やかな声かけは、赤ちゃんにとっての「最初の言葉の教育」でもあるのです。
自尊心を育てる3つのポイント
赤ちゃんの「しつけ」は、命令や禁止ではなく、自尊心(自分を大切に思う気持ち)を育てることから始まります。
そのために、次の3つの安全を意識しましょう。
・身体的安全:けがや痛みから守ること
・情緒的安全:おどかさず、恐怖を与えないこと
・自己認識の確立:「あなたは大切な存在だよ」と伝え続けること
この3つがそろうと、赤ちゃんは「自分は守られている」と感じ、健やかな成長へとつながります。
睡眠不足でも「怒らないしつけ」を心がけましょう
新生児期は昼夜の区別がなく、夜中でも数時間ごとに目を覚まします。
お母さんが寝不足になるのは当然のことです。
しかし、イライラしたまま怒鳴ったり、焦ってあやそうとしたりすると、赤ちゃんに不安が伝わってしまいます。
どうしても疲れたときは、家族やサポートサービスを頼りましょう。
「お母さんが笑顔でいられること」こそが、赤ちゃんにとって最高のしつけです。
新生児期の「しつけ」は、お母さんの穏やかなまなざしから
0歳児のしつけは、何かを教え込む時期ではなく、「安心」を積み重ねる期間です。
お母さんの安定した心が、赤ちゃんの心の安定をつくります。
泣いたらまず深呼吸して、「この子は何を伝えたいんだろう」と観察してみましょう。
焦らず、比較せず、今目の前の赤ちゃんと向き合うこと。
それが、もっとも大切な「はじめてのしつけ」です。
2025.10.30
アドラー心理学に基づいた講座です。
アルフレッド・アドラーの考え方は、現代の人間関係に十分お役に立てる内容であり、人を理解する態度、対応、勇気づけは、多くの人を癒してきました。その内容を余すところなくお伝えし、家族や職場など多くの場で活用できるものです。カウンセラーとしてのコースにも進むことができます。
2026年度コース
日程: 1/18、25、2/8、22、3/8、 22、4/12、26, 5/10、24
日曜日 全10回 10:00~12:00
講師:坂本州子(アドラー心理学心理療法士)
参加費:250,000円(分割可)
申し込み:HPの申し込みから
振込先:三菱UFJ銀行 飯田橋支店 (普)3555510
名義:サカモトクニコ
(受講、前日までにお支払いください)
2025.10.30
年内最後の子育て講座のご案内です。
1,子育て集中講座
特に今、家庭内でのお困りごとにお役に立てる内容です。
日時:11/16, 23, 30, 12/7, 14(日曜日:10:00~11:30)
参加費:全コース 5回 50,000円(2分割可)
支払い:コース開催前までにお振込みください
振込先:三菱UFJ銀行 飯田橋支店 (普)3555510
名義:サカモトクニコ
2,親子の絆つくり講座
0~3歳までの子育て中の方対象。性格形成期にも関係し
ている重要な時期です。
日時:11/27、12/11、18、25, 1/9(木曜日:10:00~11:30)
参加費:全コース5回 50,000円(5分割可)
支払い:コース開催前までにお振込みください
振込先:三菱UFJ銀行 飯田橋支店 (普)3555510
名義:サカモトクニコ
初めての育児で不安なお母さんへ。赤ちゃんとの向き合い方と心のゆとり
2025.10.30
はじめて赤ちゃんを育てるお母さんの多くは、かわいい表情やしぐさに癒されながらも、「本当にこれでいいのだろうか」と不安を感じます。
SNSや育児書、周囲の意見など、情報があふれる今だからこそ、他人と比べて焦ったり、自分の育児に自信をなくしたりしてしまう方も少なくありません。
しかし、育児に正解はありません。
もっとも大切なのは、赤ちゃんを「ひとりの人間として尊重する姿勢」です。
この記事では、赤ちゃんとの関わりを深めるための5つの視点をもとに、心が軽くなる子育てのヒントを紹介します。
民主的な対応
赤ちゃんはまだ言葉を理解できませんが、お母さんの声の調子や表情から、感情を敏感に感じ取っています。
たとえ疲れていても「今日はちょっと疲れているけど、あなたのことは大好きよ」と伝えることで、赤ちゃんは安心します。
感情的に怒ったり、無視したりするのではなく、赤ちゃんの尊厳を認める「民主的な対応」が信頼の土台になります。
赤ちゃんを「育てる対象」ではなく、「対話する相手」として見つめることが、育児の第一歩です。
子どもを理解した対応を
赤ちゃんのコミュニケーション手段は「泣く」ことです。
お腹がすいた、眠い、遊んでほしいなど、泣き方で多くを伝えようとしています。
あわてて抱き上げる前に「どんな理由で泣いているのか」を観察してみましょう。
慣れてくると、泣き方の違いで要求がわかるようになります。
また、「泣いたら抱く」を繰り返すと、赤ちゃんは「泣けば抱いてもらえる」と学び、お母さんの負担が増えることも。
大切なのは、赤ちゃんを一方的に守るのではなく、観察しながら信頼関係を築くことです。
子どもを勇気づける対応を
赤ちゃんが成長し、少しずつ言葉を話すようになったら、「ありがとう」「助かるわ」「うれしいね」と声をかけましょう。
これは単なるしつけではなく、子どもの心を育てる「勇気づけ」の言葉です。
ほめられることで子どもは「自分は認められている」と感じ、内面に自信が育ちます。
結果として「やってみよう」「できた!」という意欲が生まれ、行動力や思いやりの土台になります。
お母さんは精神的ゆとりを
育児は思いどおりにいかないものです。
「泣かれるとイライラする」「ほかの子と比べて成長が遅い気がする」と感じるのは自然なことです。
しかし、お母さんが不安でいると、赤ちゃんもその気持ちを敏感に感じ取ります。
「完璧な母親」を目指すのではなく、「今の自分でいい」と受け入れることが何より大切です。
もし疲れを感じたら、少し休んで、自分の心のケアを優先してもかまいません。
お母さんが穏やかであることが、赤ちゃんにとって最高の安心です。
お母さんの考え方を大切に
子育てでは、「他人と比べない」「情報に振り回されない」ことがポイントです。
親として一貫した考えをもち、「自分はどうしたいか」を軸に判断できれば、どんな状況でもブレません。
お母さんの考えがしっかりしていれば、赤ちゃんも迷わず安心して育ちます。
親が自分の価値観を押しつけるのではなく、行動で生き方を示すことで、子どもは自然と学んでいきます。
完璧を目指さず、共に育つ時間を大切に
初めての育児では、不安や戸惑いはつきものです。
けれど、赤ちゃんにとって必要なのは「完璧なお母さん」ではなく、「安心できるお母さん」です。
泣き声に耳を傾け、成長を見守り、たまに自分を休ませる。そんな日々の積み重ねこそが、親子の信頼を深め、心を豊かにしてくれます。